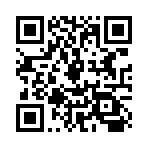2016年10月28日
仕事のストレスによるうつ発症、医療業が第2位。看護師のストレス原因は「仕事量」
仕事のストレスによるうつ発症、医療業が第2位。看護師のストレス原因は「仕事量」
仕事による強いストレスが原因で精神障害を発症し、労災請求をした業種のトップは「社会福祉・介護事業」。第2位が「医療業」であることがわかりました。
職種別の労災請求でも「介護サービス事業者」が第5位、「保健師、助産師、看護師」が第9位と上位に…。日本医労連の調査では、全産業の労働者と比較して、看護職は健康に対して不調に感じる程度が18ポイント多いという結果になっています。
http://www.irouren.or.jp/research/
「仕事量」「医療事故の不安」がストレスに
看護師が感じる強いストレスの要因は、「仕事量の問題」が46.6%と最多。「仕事の質の問題」が30.3%、「職場の人間関係」28.4%、「仕事への適性の問題」19.8%、「事故の不安」11.9%と続きます。これを全産業の労働者が感じているストレスと比較すると、「仕事の量」で20ポイント高く、全産業の「事故や災害」に比べて「医療事故の不安」が10ポイント上回っていました。
6割が薬を服用、向精神薬も1割に
看護職の6割が何らかの薬を常用していて、最も多いのが「鎮痛剤」で焼く3割、「睡眠剤」や「安定剤」「抗うつ剤」など向精神薬を服用している人も1割を占めていて、精神疾患を抱えつつ働いている人が一定数以上いることが分かりました。
メンタルヘルスの労災申請で医療職が上位を占める傾向は長年続いていて改善する様子がみえません。昨年から事業主によるストレスチェック制度が義務づけされた今、何よりもまず医療現場のメンタルヘルス対策が急務といえそうです。(ステキナース研究所より)
https://www.kango-roo.com/
仕事による強いストレスが原因で精神障害を発症し、労災請求をした業種のトップは「社会福祉・介護事業」。第2位が「医療業」であることがわかりました。
職種別の労災請求でも「介護サービス事業者」が第5位、「保健師、助産師、看護師」が第9位と上位に…。日本医労連の調査では、全産業の労働者と比較して、看護職は健康に対して不調に感じる程度が18ポイント多いという結果になっています。
http://www.irouren.or.jp/research/
「仕事量」「医療事故の不安」がストレスに
看護師が感じる強いストレスの要因は、「仕事量の問題」が46.6%と最多。「仕事の質の問題」が30.3%、「職場の人間関係」28.4%、「仕事への適性の問題」19.8%、「事故の不安」11.9%と続きます。これを全産業の労働者が感じているストレスと比較すると、「仕事の量」で20ポイント高く、全産業の「事故や災害」に比べて「医療事故の不安」が10ポイント上回っていました。
6割が薬を服用、向精神薬も1割に
看護職の6割が何らかの薬を常用していて、最も多いのが「鎮痛剤」で焼く3割、「睡眠剤」や「安定剤」「抗うつ剤」など向精神薬を服用している人も1割を占めていて、精神疾患を抱えつつ働いている人が一定数以上いることが分かりました。
メンタルヘルスの労災申請で医療職が上位を占める傾向は長年続いていて改善する様子がみえません。昨年から事業主によるストレスチェック制度が義務づけされた今、何よりもまず医療現場のメンタルヘルス対策が急務といえそうです。(ステキナース研究所より)
https://www.kango-roo.com/
Posted by 熊本県医療介護福祉労働組合連合会 at
06:03
│Comments(0)
2016年10月27日
組合こぼれ話「社会保障のこと」
「社会保障」と聞いて、皆さんは何を思い浮かべますか。ニュースなどでよく耳にするのは、政府が消費税率を引き上げる際に必ず理由として持ち出す「社会保障のため」という言葉でしょうか。
本来は赤ちゃんからお年寄りまですべての国民に「健康で文化的な最低限度の生活(憲法25条)」を保障するのが「社会保障」です。
「社会保障」はすべての国民に等しく保障されている権利であり、医療や介護・福祉、また年金や生活保護など、さまざまな形で国民の「生存権」を支えるしくみとして機能しています。
●医療の仕事と「社会保障」のかかわりとは?
医療や介護の現場の人手不足は深刻です。日本全国どこの病院・介護施設でも、多少の差はあれ慢性的な人員不足を抱え、誰もが仕事の質や量に見合わない賃金に不満を持っています。
多くの看護師が、夜勤を含む勤務の大変さに耐えかねて離職してしまうのが人手不足の原因だとすれば、「給料をもっと増やして」「職場にもっと人手を増やして」毎日やりがいを実感しつつ、ゆとりをもって働ける職場にすればいいのでは…。それこそが労働組合の目指す医療・介護の職場のあるべき姿なのですが、そうならない理由があります。
実は、そうした職場の抱える人手不足や賃金の問題と「社会保障」には深いかかわりがあるのです。
医療・看護・介護の現場においては、病院や施設の構造、部屋の広さや廊下の幅などだけでなく、病棟やユニットに看護師や介護職員を何人配置すべきか、すべて基準が決められています。こうした基準は、入院患者さんなどが療養生活を送るのに適した環境を保障し、そこで提供される看護や介護の質を保障するために、医療法や介護保険法などに基づいて定められているものです。
スタッフも職場責任者(師長・課長)も、病院長・施設長も、この決められた基準に従って医療・介護を提供しています。つまり、サービスの質、量を決める上で決定的な意味をもつ基準を定めている国が、患者さんなどに対し適切な医療・介護を保障する責任を負っているということです。
>人手が増えないように仕組まれている?
看護や介護の職場で基本的な人員配置基準が定められていることは、現場で働く皆さんがよくご存じのとおりです。
国のきめられた基準が守られているかどうかについては保健所や厚生局から厳しいチェックを受け、守られていないと判断されれば規定どおりの収入も入ってきません。
万一、不正などがあった場合は、開業の許可さえ取り消されてしまうという厳格なものです。
しかし、この厳しい配置基準が守られているはずなのに、どこもかしこも人手不足という現状を見ると、実は大元の基準そのものに問題があるのでは…と考えざるを得ません。
●「基準」そのものの改善を求めることが必要
決められた人数を守らないと「監査に引っかかる」とは、院内でもよく言われることですが、それなら多い分には問題ないのでは?
ところが、そう単純にはいかない事情があり、人員配置とそれに応じた報酬の規定がこれに関わっているのです。
例えば検査や投薬、手術・処置などは、たくさん行えばそれだけ点数がカウントされ、診療報酬も増える仕組みです。医師を確保して手術の回数を多くすれば、医師の人件費や経費はかかりますが、利益もあげられるというわけです。
しかし看護や介護においては、入院基本料などの、配置基準に応じた定額収入が基本なので人を増やしても収入は増えません。人が増えれば、その分1人あたりにかけられる人件費が減ることになってしまいます。職場に人手が足りない現状の背後には、このような構造的な問題が仕込まれていたのです。
もちろん実際には看護師や介護職員の給料は、入院基本料などだけでなく、病院や施設の経営全体のやりくりの中でまかなわれています。だからこそ労働組合は、病院・施設のトップに対し、賃金の引き上げや増員を求めてしっかり交渉を続けていく必要があります。
それと同時に、全国的な人手不足をうむ要因となっている'カラクリ'、すなわち国の決めた基準そのものの改善を求めていくことが大事です。
>昔の医療と今の医療、何が変わった?
40歳代後半~50歳代のベテランの人なら、入院していた患者さんが良くなって歩いて退院していく姿を見送るのが日常的な光景だったと記憶しているでしょう。
ところが今は、夜勤のクールが明けて日勤で出てきたら、受け持ち患者さんが退院していたなどということも珍しくなく、酸素吸入したままストレッチャーで搬送車へ、というような場合さえあります。
以前は1か月くらいかけて入院治療を行っていたケースでも、今は入院期間3~7日といった早期退院は当たり前です。そこには確かに医療のめざましい進歩・発展があり、医療従事者はそれを精一杯支えています。
しかしながら、早期介入・早期離床・早期退院の流れは、必ずしも臨床上の必要からそうなっているわけではありません。例えば身体機能の回復や維持を目指すリハビリテーションでは、患者さん個々の状態を考慮せず日数で区切り、維持期になれば医療から切り離して介護保険で、という実情にもあらわれています。
また、入院患者の医療・看護必要度を毎日チェックするには、それに応じたケア計画を立てるのは主眼というよりも、病棟から退出してもらう患者さんを選ぶためにひつようなこととなってしまっています。
●「効率化」の追求が、現場や利用者の負担増に
今から10年ほど前、相次ぐ医療事故が問題となり「根拠に基づく医療(EBM)」が強調されるなか、DPCが制度化されました。看護の現場ではクリティカルパスの導入がすすめられ、医療機関の連携を橋渡しする地域連携パスも考案されました。
いずれも、より効率的な医療・看護の実現には貢献しています。
DPC以前には、入院後に検査・手術が標準だったのが、外来通院ですべて検査を終え、手術直前の入院が一般的になりました、在院日数の短縮には大いに貢献する一方、入退院サイクルは早くなり、看護現場は高速回転状態になり、患者さんや家族の方には物理的・肉体的・精神的な負担増を強いています。
日本の医療はいま、人材や施設に限りがあるという問題も含めて、様々な制約を課せられ、狭い枠の中でより効率化することを求められ続けています。
本来は赤ちゃんからお年寄りまですべての国民に「健康で文化的な最低限度の生活(憲法25条)」を保障するのが「社会保障」です。
「社会保障」はすべての国民に等しく保障されている権利であり、医療や介護・福祉、また年金や生活保護など、さまざまな形で国民の「生存権」を支えるしくみとして機能しています。
●医療の仕事と「社会保障」のかかわりとは?
医療や介護の現場の人手不足は深刻です。日本全国どこの病院・介護施設でも、多少の差はあれ慢性的な人員不足を抱え、誰もが仕事の質や量に見合わない賃金に不満を持っています。
多くの看護師が、夜勤を含む勤務の大変さに耐えかねて離職してしまうのが人手不足の原因だとすれば、「給料をもっと増やして」「職場にもっと人手を増やして」毎日やりがいを実感しつつ、ゆとりをもって働ける職場にすればいいのでは…。それこそが労働組合の目指す医療・介護の職場のあるべき姿なのですが、そうならない理由があります。
実は、そうした職場の抱える人手不足や賃金の問題と「社会保障」には深いかかわりがあるのです。
医療・看護・介護の現場においては、病院や施設の構造、部屋の広さや廊下の幅などだけでなく、病棟やユニットに看護師や介護職員を何人配置すべきか、すべて基準が決められています。こうした基準は、入院患者さんなどが療養生活を送るのに適した環境を保障し、そこで提供される看護や介護の質を保障するために、医療法や介護保険法などに基づいて定められているものです。
スタッフも職場責任者(師長・課長)も、病院長・施設長も、この決められた基準に従って医療・介護を提供しています。つまり、サービスの質、量を決める上で決定的な意味をもつ基準を定めている国が、患者さんなどに対し適切な医療・介護を保障する責任を負っているということです。
>人手が増えないように仕組まれている?
看護や介護の職場で基本的な人員配置基準が定められていることは、現場で働く皆さんがよくご存じのとおりです。
国のきめられた基準が守られているかどうかについては保健所や厚生局から厳しいチェックを受け、守られていないと判断されれば規定どおりの収入も入ってきません。
万一、不正などがあった場合は、開業の許可さえ取り消されてしまうという厳格なものです。
しかし、この厳しい配置基準が守られているはずなのに、どこもかしこも人手不足という現状を見ると、実は大元の基準そのものに問題があるのでは…と考えざるを得ません。
●「基準」そのものの改善を求めることが必要
決められた人数を守らないと「監査に引っかかる」とは、院内でもよく言われることですが、それなら多い分には問題ないのでは?
ところが、そう単純にはいかない事情があり、人員配置とそれに応じた報酬の規定がこれに関わっているのです。
例えば検査や投薬、手術・処置などは、たくさん行えばそれだけ点数がカウントされ、診療報酬も増える仕組みです。医師を確保して手術の回数を多くすれば、医師の人件費や経費はかかりますが、利益もあげられるというわけです。
しかし看護や介護においては、入院基本料などの、配置基準に応じた定額収入が基本なので人を増やしても収入は増えません。人が増えれば、その分1人あたりにかけられる人件費が減ることになってしまいます。職場に人手が足りない現状の背後には、このような構造的な問題が仕込まれていたのです。
もちろん実際には看護師や介護職員の給料は、入院基本料などだけでなく、病院や施設の経営全体のやりくりの中でまかなわれています。だからこそ労働組合は、病院・施設のトップに対し、賃金の引き上げや増員を求めてしっかり交渉を続けていく必要があります。
それと同時に、全国的な人手不足をうむ要因となっている'カラクリ'、すなわち国の決めた基準そのものの改善を求めていくことが大事です。
>昔の医療と今の医療、何が変わった?
40歳代後半~50歳代のベテランの人なら、入院していた患者さんが良くなって歩いて退院していく姿を見送るのが日常的な光景だったと記憶しているでしょう。
ところが今は、夜勤のクールが明けて日勤で出てきたら、受け持ち患者さんが退院していたなどということも珍しくなく、酸素吸入したままストレッチャーで搬送車へ、というような場合さえあります。
以前は1か月くらいかけて入院治療を行っていたケースでも、今は入院期間3~7日といった早期退院は当たり前です。そこには確かに医療のめざましい進歩・発展があり、医療従事者はそれを精一杯支えています。
しかしながら、早期介入・早期離床・早期退院の流れは、必ずしも臨床上の必要からそうなっているわけではありません。例えば身体機能の回復や維持を目指すリハビリテーションでは、患者さん個々の状態を考慮せず日数で区切り、維持期になれば医療から切り離して介護保険で、という実情にもあらわれています。
また、入院患者の医療・看護必要度を毎日チェックするには、それに応じたケア計画を立てるのは主眼というよりも、病棟から退出してもらう患者さんを選ぶためにひつようなこととなってしまっています。
●「効率化」の追求が、現場や利用者の負担増に
今から10年ほど前、相次ぐ医療事故が問題となり「根拠に基づく医療(EBM)」が強調されるなか、DPCが制度化されました。看護の現場ではクリティカルパスの導入がすすめられ、医療機関の連携を橋渡しする地域連携パスも考案されました。
いずれも、より効率的な医療・看護の実現には貢献しています。
DPC以前には、入院後に検査・手術が標準だったのが、外来通院ですべて検査を終え、手術直前の入院が一般的になりました、在院日数の短縮には大いに貢献する一方、入退院サイクルは早くなり、看護現場は高速回転状態になり、患者さんや家族の方には物理的・肉体的・精神的な負担増を強いています。
日本の医療はいま、人材や施設に限りがあるという問題も含めて、様々な制約を課せられ、狭い枠の中でより効率化することを求められ続けています。
Posted by 熊本県医療介護福祉労働組合連合会 at
12:30
│Comments(0)