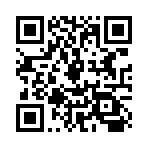2016年12月14日
ハラスメントの放置は重大な法違反に。
年々増加傾向のハラスメントの相談ですが、被害者がパワハラの加害行為を違法なものであるとの認識になく、訴え出る事ができず被害が深刻化しやすい傾向にあると感じます。
なんとなくハラスメント被害だと感じているけど、企業がきちんと対応をしなければならなかったことと知らなかったため訴えでず我慢していたというケースも少なくありません。
今日は、職場のハラスメントがどのような法律に係るのかを書きたいと思います。
厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」提言によると、パワハラとは「職務上の地位や人間関係など職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させたりする行為」と定義。
「上司から部下」へのいじめや嫌がらせだけでなく、「同僚間」や「部下から上司」に対するものも含まれるとしています。
パワハラは働く人の誰もが当事者になり得るとして、働くすべての人が問題を意識し取り組むことを求めているものです。
また、典型的なパワハラを6類型に整理し、
①身体的な攻撃=暴行・傷害
②精神的な攻撃=脅迫・侮辱
③人間関係からの切り離し=隔離・仲間外し
④過大な要求=遂行不可能なことの強制
⑤過小な要求=能力や経験とかけ離れて程度の低い仕事を命じること
⑥個の侵害=私的なことへの過度な立ち入り
と具体例とともに示しています。
企業には、労働者の心身を健全に保つことができるように、職場環境をそれにふさわしく整える義務(安全配慮義務)があり、
2008年3月1日施行された労働契約法第5条に「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」
と定められました。
パワハラ対策は、パワハラが違法行為であることを認識することが問題解決の第一歩です。
企業に対しては以下の法的責任が課せられています。
(1) 使用者には、労働者が労務を提供するに当たり、人格的尊厳を侵し、その労務提供に重大な支障を来す事由が発生することを防ぎ、
またはこれに適切に対処して、職場が労働者にとって働きやすい環境を保つように配慮する注意義務があります。
この義務は、セクハラ防止のための「就業環境配慮義務」として雇用機会均等法第21条に盛り込まれました。
(2) したがって、使用者が、いじめ、パワハラが起こっている環境を知りながら放置しているような場合は、
企業そのものに、安全配慮義務・就業環境配慮義務違反ということで賠償責任が発生します(民法709条)。
(3) 現実に人格権侵害行為を行った上司や同僚は、当然に不法行為責任(民法709条)を負います。
(4) 使用者の意思に基づき管理職を通じて人格権侵害をおこなった場合には、使用者責任(民法715条)を負います。
(5) 使用者意思に基づかない上司、同僚らによる人格権侵害の場合、当該行為を行った上司や同僚は不法行為責任(民法709条)を負うことは当然ですが
、同僚らによるいじめやセクハラが「事業の執行につき」行われた場合には、使用者は民法715条に基づいて、被害者に対して損害賠償義務を負います。
なんとなくハラスメント被害だと感じているけど、企業がきちんと対応をしなければならなかったことと知らなかったため訴えでず我慢していたというケースも少なくありません。
今日は、職場のハラスメントがどのような法律に係るのかを書きたいと思います。
厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」提言によると、パワハラとは「職務上の地位や人間関係など職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させたりする行為」と定義。
「上司から部下」へのいじめや嫌がらせだけでなく、「同僚間」や「部下から上司」に対するものも含まれるとしています。
パワハラは働く人の誰もが当事者になり得るとして、働くすべての人が問題を意識し取り組むことを求めているものです。
また、典型的なパワハラを6類型に整理し、
①身体的な攻撃=暴行・傷害
②精神的な攻撃=脅迫・侮辱
③人間関係からの切り離し=隔離・仲間外し
④過大な要求=遂行不可能なことの強制
⑤過小な要求=能力や経験とかけ離れて程度の低い仕事を命じること
⑥個の侵害=私的なことへの過度な立ち入り
と具体例とともに示しています。
企業には、労働者の心身を健全に保つことができるように、職場環境をそれにふさわしく整える義務(安全配慮義務)があり、
2008年3月1日施行された労働契約法第5条に「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」
と定められました。
パワハラ対策は、パワハラが違法行為であることを認識することが問題解決の第一歩です。
企業に対しては以下の法的責任が課せられています。
(1) 使用者には、労働者が労務を提供するに当たり、人格的尊厳を侵し、その労務提供に重大な支障を来す事由が発生することを防ぎ、
またはこれに適切に対処して、職場が労働者にとって働きやすい環境を保つように配慮する注意義務があります。
この義務は、セクハラ防止のための「就業環境配慮義務」として雇用機会均等法第21条に盛り込まれました。
(2) したがって、使用者が、いじめ、パワハラが起こっている環境を知りながら放置しているような場合は、
企業そのものに、安全配慮義務・就業環境配慮義務違反ということで賠償責任が発生します(民法709条)。
(3) 現実に人格権侵害行為を行った上司や同僚は、当然に不法行為責任(民法709条)を負います。
(4) 使用者の意思に基づき管理職を通じて人格権侵害をおこなった場合には、使用者責任(民法715条)を負います。
(5) 使用者意思に基づかない上司、同僚らによる人格権侵害の場合、当該行為を行った上司や同僚は不法行為責任(民法709条)を負うことは当然ですが
、同僚らによるいじめやセクハラが「事業の執行につき」行われた場合には、使用者は民法715条に基づいて、被害者に対して損害賠償義務を負います。
Posted by 熊本県医療介護福祉労働組合連合会 at
17:06
│Comments(0)