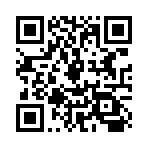2016年11月11日
組合こぼれ話「みんなのための社会保障」
「社会保障」を考える上で、忘れてならないのが患者さんや利用者さんの自己負担という問題です。
日本には「皆保険制度」があるため、健康保険証があれば全国どこの病院・診療所でも病気やけがに応じた適切な治療が受けられ、その費用も公定価格で全国一律という仕組みです。
ただし、病院で診療を受け、検査や注射・投薬をしてもらうと、患者さんは窓口で一部負担金を支払わなければなりません。
かつて、健康保険の本人や高齢者は自己負担なしという時代がありました。現在は、国保・健保の本人と家族は3割負担、高齢者は年齢や所得によって1割~3割の負担となっています。
さらに入院すると、差額ベッド代、入院給食費、紙オムツ代など結構な額が患者負担となります。自宅から遠く離れた病院に入院している場合は家族の宿泊代なども必要になる事があります。
●誰もが安心して必要な医療を受けられる社会に
こうした自己負担額が重いために病院にかかりたくてもかかれない人が増えています。
また、国民健康保険の保険料が高すぎて納めきれず、保険証の交付が受けられなくなったという人もいます。
保険証を持っていないと、基本的に医療費全額が自己負担となりますが、そもそも保険料が払えないのに医療費が支払えるはずもありません。
過去1年の間に金銭的な理由で受診を抑制したことのある人は26%、4人に1人という調査結果もあります(2013年日本医療政策機構)。病院にかかれないことで状態が悪化・重症化して手遅れになってしまうケースも少なくありません。
支払ができなくて医療を受けられない人や、入院しても治りきらないまま退院せざるを得ない患者が激増し「医療難民」という言葉が生まれて社会問題化しています。このような現状は医療従事者にとっても不幸なことといえます。
医療・介護・福祉サービスを十分に提供できる体制があり、その受け手である国民が、いつでもどこでも誰でも金銭的な心配なく、必要なだけサービスを受けられる世の中であることが、本来の「社会保障」のあり方ではないでしょう?
日本には「皆保険制度」があるため、健康保険証があれば全国どこの病院・診療所でも病気やけがに応じた適切な治療が受けられ、その費用も公定価格で全国一律という仕組みです。
ただし、病院で診療を受け、検査や注射・投薬をしてもらうと、患者さんは窓口で一部負担金を支払わなければなりません。
かつて、健康保険の本人や高齢者は自己負担なしという時代がありました。現在は、国保・健保の本人と家族は3割負担、高齢者は年齢や所得によって1割~3割の負担となっています。
さらに入院すると、差額ベッド代、入院給食費、紙オムツ代など結構な額が患者負担となります。自宅から遠く離れた病院に入院している場合は家族の宿泊代なども必要になる事があります。
●誰もが安心して必要な医療を受けられる社会に
こうした自己負担額が重いために病院にかかりたくてもかかれない人が増えています。
また、国民健康保険の保険料が高すぎて納めきれず、保険証の交付が受けられなくなったという人もいます。
保険証を持っていないと、基本的に医療費全額が自己負担となりますが、そもそも保険料が払えないのに医療費が支払えるはずもありません。
過去1年の間に金銭的な理由で受診を抑制したことのある人は26%、4人に1人という調査結果もあります(2013年日本医療政策機構)。病院にかかれないことで状態が悪化・重症化して手遅れになってしまうケースも少なくありません。
支払ができなくて医療を受けられない人や、入院しても治りきらないまま退院せざるを得ない患者が激増し「医療難民」という言葉が生まれて社会問題化しています。このような現状は医療従事者にとっても不幸なことといえます。
医療・介護・福祉サービスを十分に提供できる体制があり、その受け手である国民が、いつでもどこでも誰でも金銭的な心配なく、必要なだけサービスを受けられる世の中であることが、本来の「社会保障」のあり方ではないでしょう?
Posted by 熊本県医療介護福祉労働組合連合会 at
15:47
│Comments(0)